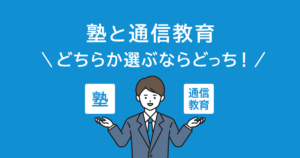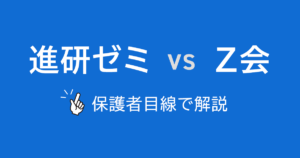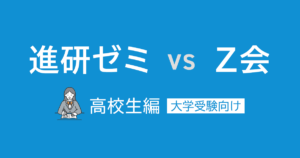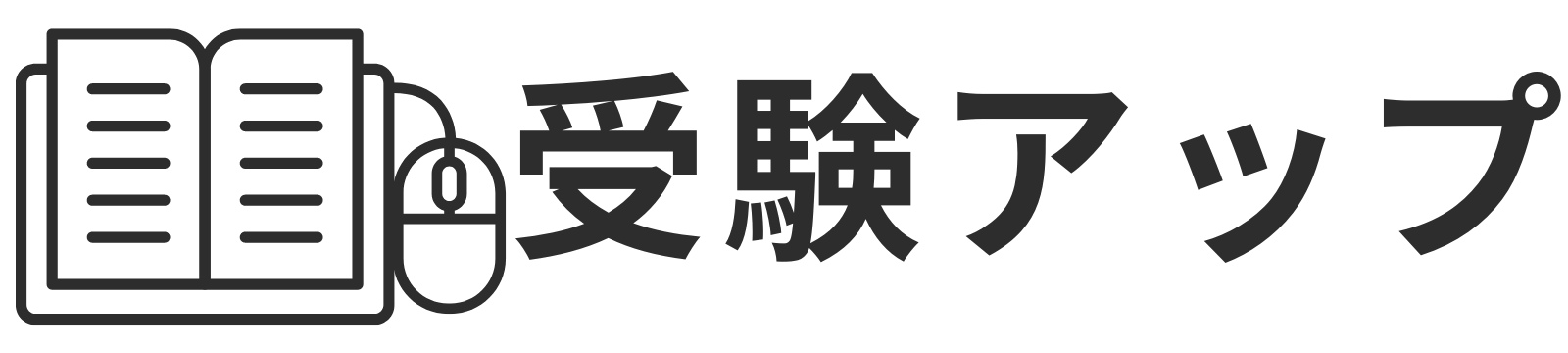現在、塾に通っているけれど、「進研ゼミも併用したほうがいいのか?」と迷っていませんか?
「2つの学習を両立できるのか?」「進研ゼミの評判は?」「効果はあるの?」といった不安をお持ちの方も多いでしょう。
本記事では、塾と進研ゼミを併用するメリット・デメリットや、実際に続けるコツ を詳しく解説します。後悔しない選択をするために、ぜひ最後までご覧ください!
受験を控え、「もっと成績を上げたい!」と考えている学生さんや保護者の方にとって、塾と通信教育の併用 は大きなテーマですよね。
「2つの学習を両立できるのか?」
「どっちつかずになってしまわないか?」
塾は強制的に学習のリズムを作ってくれる一方で、通信教育は自分で進める力が必要 です。そのため、「子どもが続けられるのか?」と不安を感じる保護者の方も多いでしょう。実際、塾講師をしていた頃にも、そうした悩みを持つ親御さんを何度も見てきました。
しかし、適切なやり方をすれば、塾と進研ゼミの併用は効果的 だと考えています。
そのカギとなるのは 「科目数を絞ること」 です。
本記事では、実際に進研ゼミを利用した筆者が、コスト面も考慮しながら、塾との効果的な併用方法やメリット を詳しく解説します。
では、早速見ていきましょう!
進研ゼミと塾を両立させるカギ

進研ゼミと塾を完璧に両立させるのは決して簡単なことではありません。この点は、事前に理解しておくことが大切です。
進研ゼミは1教科あたり約15分の学習時間を想定していますが、5教科すべて受講すると 1時間半以上 必要になります。塾の宿題や学校の課題も考えると、すべてを完璧にこなすのは相当な負担になります。
そのため、効果的に併用するためには科目数を絞ることが重要 です。
塾と進研ゼミの最適な使い分け
私が中学生のときに実践していたのは、以下のような使い分けです。
塾・予備校→得意科目
進研ゼミ→苦手科目
という使い分けをしていました。
塾ではハイレベルな内容を学べる一方で、進研ゼミは生徒一人ひとりに合ったレベルの教材 を提供してくれます。そのため、苦手科目の克服には進研ゼミが最適でした。
「進研ゼミの効果を解説!意味ないと言われるのはなぜ?」の記事でも触れていますが、塾は基本的にクラス全体のレベルに合わせるため、ついていけない生徒に個別対応することは難しい です。
私自身、特に理数が苦手で、塾の授業どころか学校の内容ですら怪しいレベルでした。そこで、進研ゼミで基礎固め を徹底したところ、最終的には偏差値70を超える難関校の入試でも足を引っ張らないレベルまで到達できました。
もし塾だけに頼っていたら、おそらく苦手科目を克服できず、諦めてしまっていたと思います。
進研ゼミと塾の併用は「戦略的に」
進研ゼミと塾を両立するためには、「すべて完璧にこなす」のではなく、「必要な部分に絞って活用する」 ことが大切です。
✅ 得意科目は塾で伸ばす
✅ 苦手科目は進研ゼミで基礎固め
この戦略を意識すれば、無理なく両立でき、学習効果も最大化できます!
進研ゼミと塾の両立に関して寄せられた質問
進研ゼミと塾の併用については、多くの人が関心を持っており、Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでもよく議論されています。実際に、以下のような質問を目にすることが多いです。
実際に寄せられた質問(Yahoo!知恵袋より)
「進研ゼミをやって成績が上がった人はいますか?」
「中学2年生の子どもが学習塾に通っているものの、成績が伸びません。
進研ゼミを併用させるか、それとも子どもが希望している進研ゼミ一本にするか悩んでいます。
進研ゼミって実際どうなんでしょう? 5教科すべて受講しても月数千円で済みますが、塾では数学と英語だけでも月18,000円ほどかかります。
自宅での自己学習だけで、本当に成績は伸びるのでしょうか?」
この質問に対して、多くの回答が寄せられました。その中で、特に的を射た意見をご紹介します。
実際の回答(Yahoo!知恵袋より)
「うちの娘は進研ゼミで成績が上がりました。
それまでは仲の良い友達と一緒に個別指導塾に通っていましたが、通塾時間がもったいないと感じるようになり、友達と一緒に進研ゼミで勉強することにしました。
真面目な友達だったので、お互いに教え合う形で学習が進んでいきました。
週に1回、一緒に勉強し、それ以外は自宅学習でしたが、それでも十分な成果が出ました。一方で、別の同級生は家庭教師までつけたのに成績が伸びませんでした。
その違いは、「勉強のやり方」 にあると思います。
ただ授業を受けるだけで満足してしまったり、学習中に集中できなかったりすると、どれだけお金をかけても成果は出にくいです。実際に、塾に通えなかった部活生でも進研ゼミだけで偏差値65の公立高校に合格した人もいますし、何も習わずにオール5を取って進学校に進んだ人もいます。」
塾に行っても成績が伸びないのはなぜ?
このQ&Aから見えてくる最大のポイントは、塾に通っていても成績が伸びない人は一定数いる ということです。
さらに掘り下げて考えると、塾で伸びにくいのは「苦手科目」であるケースが多い ことに気づきます。
その原因は、塾の講義スタイル にあります。
塾の授業の特徴と限界
塾では、生徒に対して授業を与えることで強制的に学習させる仕組みになっています。言い換えれば、「受け身の学習」 になりがちです。
✔ 得意科目の場合
塾の授業についていけるので、発展的な内容を学ぶことで応用力が自然と身についていきます。
また、クラスメイトと教え合うことで、さらに理解が深まるケースもあります。
✔ 苦手科目の場合
授業のスピードについていけず、分からない部分がそのままになりがちです。
結果として「授業を受けただけ」で終わってしまい、学力の向上につながらないことが多くなります。
つまり、苦手科目を克服するには、ただ塾に通うだけでは不十分 なのです。
そこで、進研ゼミを活用することで、苦手科目を基礎から学び直す という選択肢が生まれます。
このように、塾と進研ゼミの使い分けを戦略的に考えることで、より効果的な学習が可能になるのです。
私が実際に両立してみて思ったこと

私も中学生の頃、進研ゼミと塾を併用していました。
当時、私はサッカー部に所属しており、時間の余裕がない ことに加え、母子家庭で経済的な負担も考えなければならない 状況でした。そのため、塾と進研ゼミを戦略的に使い分ける必要がありました。
私が選択した受講科目は以下の通りです。
✅ 塾 → 英語・数学
✅ 進研ゼミ → 理科・数学
私はもともと文系タイプ だったので、社会や国語は受験直前まで特に対策せず、苦手だった数学を重点的に強化する形をとりました。
なぜ数学を塾と進研ゼミの両方で受講したのか?
ここまで読んで、「塾=得意科目」「進研ゼミ=苦手科目」 と書いたのに、なぜ数学(苦手科目)を塾でも受講しているのか?と疑問に思う方もいるかもしれません。
実は私の場合、時間が限られていたので、以下の戦略を取りました。
✔ 基礎的な部分 → 進研ゼミでしっかり固める
✔ 応用的な部分 → 塾でカバーする
結果的に、これが大成功。
基礎をしっかり理解したことで、応用問題にも取り組む力がつき、数学の偏差値を20近く伸ばすことができました。
塾で苦手科目を特訓している友達を見て、「自分は遠回りしているのでは?」と感じたこともありました。しかし、苦手科目こそ、基礎を固めてから応用に進む方が最短ルート だったと、今では確信しています。
数学は塾で受けたほうが良い理由
余談ですが、高校受験の数学では「答えのみ」が求められる ことが多いです。(大学受験では途中式の記入が必要で、部分点が加算されます)
そのため、塾では学校や進研ゼミでは教えてくれない「解答テクニック」 を学ぶことができました。
例えば、三角形の面積を一瞬で求める公式 など、計算時間を短縮できる裏技 を教えてくれるのは塾ならではの強みです。
これらの理由から、数学だけは無理をしてでも塾で受講しておくメリットが大きい と感じています。
進研ゼミと塾の併用を考えている方は、ぜひ 「基礎は進研ゼミ」「応用は塾」 というバランスを意識してみてください!
進研ゼミと塾を併用するうえで注意しておきたいこと
進研ゼミと塾を併用する際に、最も大切なのは 「科目を絞ること」 です。
もう一度、私が受講していた科目を振り返ってみましょう。
✅ 塾 → 英語・数学
✅ 進研ゼミ → 理科・数学
進研ゼミでは 理科と数学の2科目のみ を選択し、社会・国語・英語には手を広げませんでした。
これは、むやみに全科目を受講しない という戦略です。
ポイントは、「自分でできる科目には手をつけない」こと。
塾と進研ゼミを併用すると、どうしても学習量が増え、負担が大きくなります。すべての教科をカバーしようとすると、どれも中途半端になり、結局「どっちつかず」になってしまう可能性が高いのです。
そのため、「塾で伸ばしたい科目」「進研ゼミで補強したい科目」を明確に分けることが、効率的に両立するカギ になります。
自分の得意・不得意を把握し、限られた時間とエネルギーを最大限活用できるように、必要な科目だけに絞って受講すること をおすすめします。
>>進研ゼミの効果を解説(こちらの記事で科目の絞り方を詳しく解説しています)
両立するうえで保護者の方には「捨てる」決断をしてもらう必要がある
「じゃあ、苦手科目の受講だけすればいいのね!」とシンプルに割り切れれば楽なのですが、実際にはそれが難しい のが現実です。
進研ゼミの中学生講座は5教科パック で提供されるため、苦手科目に絞ると、手をつけない教材が出てきます。
(私の場合、進研ゼミで受講していたのは理科と数学のみだったため、社会・英語・国語の教材はほとんど手をつけませんでした。)
ここで重要なのが、保護者の理解とサポートです。
「もったいない」発想が、子どもの負担を増やす
進研ゼミの教材をすべて活用できないことに対し、「せっかくお金を払っているのだから、全教科やりなさい!」 と言いたくなる気持ちは分かります。
しかし、この考え方は危険です。
✔ 無理に全教科やらせようとすると…
➡ 子どもは苦手科目よりも、やらなくてもできる得意科目に時間を取られる
➡ 苦手科目の対策が疎かになり、成績が伸びない
➡ 「頑張ってるのに成果が出ない…」とモチベーションが下がる
こうして、本来の目的である「苦手科目の克服」ができず、悪循環に陥ってしまう のです。
「捨てる」勇気を持つことが大切
ここまで読んでいただいたあなたなら、もうお分かりかと思います。
✔ お子さんが進研ゼミの教材を「すべてやっていない」としても、「苦手科目に集中するために絞っている」と理解してあげてください。
✔ 「もったいないから全部やる」のではなく、「必要なものだけに集中する」ことが成績アップの近道 です。
✔ ただし、苦手科目をサボっていないかどうかは、しっかりチェックすることも重要!
進研ゼミの中学生講座は5教科セットで月6,000円台 と、塾に比べるとかなり経済的です。
また、高校生講座になると 1科目ごとに受講できるため、無駄なく選択可能 になります。
ただし、塾であっても進研ゼミであっても、最終的な目的は「経済面のメリット」ではなく、「成績を上げること」 です。
お子さんの学習効果を最大化するためにも、必要なものに集中し、無駄を省く決断 をすることが大切です。
塾と進研ゼミを使いこなそう
ここまで、塾と進研ゼミを併用する方法とそのポイント について解説してきました。
多くの保護者の方が、「進研ゼミは全教科受講し、さらに塾でも複数科目を受講すれば安心!」 と思いがちですが、これは逆効果になりやすいです。
✅ 学習量が増えすぎて、お子さんが疲弊する
✅ 結果として、どの科目も中途半端になり、成績が伸びない
それよりも、「できない科目を少しずつできるようにする」ことが最優先 です。そのための基盤として、進研ゼミを活用するのがベストな方法だと思います。
受講費が「もったいない」と感じるかもしれませんが、必要な科目に集中することで、結果的に学習の効率は大きく向上 します。ぜひ、温かく見守ってあげてくださいね。
お子さんの成績が少しでも伸びることを心から願っています!
効果的な併用のポイント
✅ 得意科目と不得意科目を明確に分ける
✅ 塾と進研ゼミ、それぞれの役割を適切に割り振る
✅ 進研ゼミは受講する科目を厳選する(欲張って全教科受講すると失敗しやすい)
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
進研ゼミについてさらに詳しく知りたい方は、進研ゼミの資料請求や以下の記事 をぜひ参考にしてみてください。